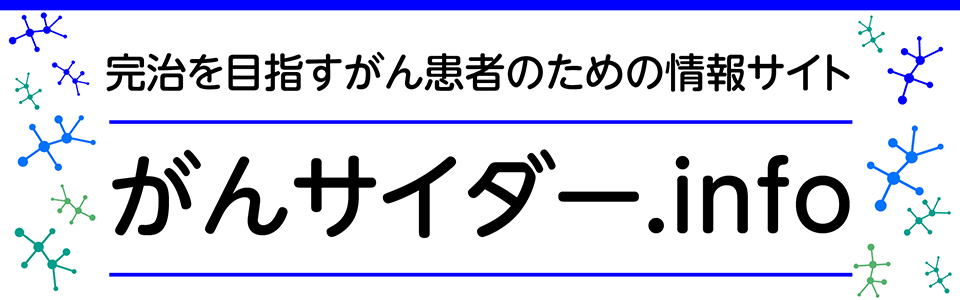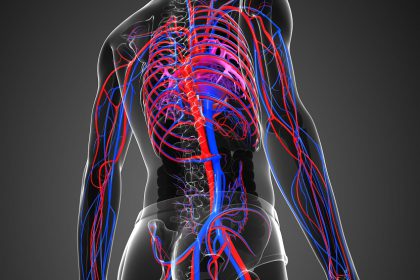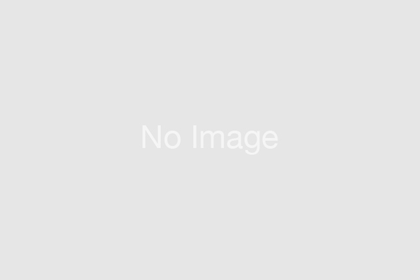ゲノム医療がもたらす日本のがん治療の変化

がんに関連する遺伝子を分析し、その変異に応じて適切な治療を選択するがん遺伝子パネル検査が保険適応になりました。リンパ球バンク代表の藤井真則氏は、このことは我が国のがん治療の方向性を変えるインパクトを持つかもしれないといいます。その可能性と実際の治療がどう変わっていくかについてお話を伺いました。
標準治療が部位別であるという状況を変えていく
――がんゲノム医療が推進される中、がん遺伝子パネル検査が保険適応になりました。
日本のがん治療は外科主導で発展してきたため、標準治療は部位別にやるべきことが決まっています。従来の抗がん剤はがん細胞内部に作用して、一時的に腫瘍を縮小させることは出来ても、がん細胞全てを排除出来ませんから、残ったがん細胞の反撃を招き、進行がんに対する治療手段としては限界がありますが、その中でも部位によっては最初から効かないことさえあります。
例えば腎臓細胞は血液の成分を分けて、尿を作るポンプ機能が強力なので、細胞内に侵入した抗がん剤を、すぐに排出して効果が出にくいのです。これに対して欧米で主流になった分子標的薬は、細胞の表面の物質に結合して作用するので、あまり部位を問いません。例えば代表的な分子標的薬であるハーセプチンは、HER2という蛋白質を目印に作用しますが、国内で保険適応となるのは、乳がんと胃がんのみです。実際には食道がんなど他の部位でもHER2は多く見られますが、保険診療では使えません。部位ごとに保険適応という現状から部位ではなくがん細胞の特性ごとに保険適応という流れに変えていくきっかけのひとつとして、がんゲノム診断が議論を呼んでいます。
――標準治療はがんゲノム医療で変わっていくのでしょうか?
先程も申し上げたように、部位ごとではなくがん細胞の性質ごとに治療を考える方向へ動くきっかけにはなるでしょう。一方、現実の治療にゲノム診断が役立つかというと、そう簡単にはいきません。今のところ、ゲノム診断の結果によって劇的に治療が変わるというケースは、殆ど見当たりません。ゲノム診断によってゲノム情報を蓄積し今後の研究に期待するという面もあります。
――科学的には正しい方向でも制度が追い付いていないと?
原理的な難しさもあります。遺伝子があるかどうかより遺伝子の活動レベルが重要です。また、がん細胞はひとつひとつが異なる性質を持っているので、たとえ隣り合ったがん細胞であっても同じ遺伝子の変異があるとは限らない。がん細胞はどんどん変異していきますから、遺伝子の変異がずっと同じではないのです。遺伝子の働きには環境、外からの刺激、複数の遺伝子がお互いに与える影響など実に様々な要因が影響します。
そうなると調べても仕方がないと思われるかもしれませんが、スーパーコンピュータがどんどん進化している時代ですから、膨大なデータを集めて、人工知能でがんがん分析していけば、何らかの答えが出るかもしれません。がん遺伝子パネル検査は保険適応の条件として遺伝情報を提供することになっていますが、方向性としては間違っていないと思います。
性質から考えれば、
明らかに使える分子標的薬は適応拡大するべき
――まだ技術的にも課題は多いということですね。
当社ではがん免疫の主役であるNK細胞の培養を行っていますが、NK細胞はがん細胞だけを正確に識別する唯一の存在といっても過言ではないでしょう。遺伝子の変異だけでは見抜けないがん細胞でも、野生型(研究用に培養されたNK細胞ではなく、ヒトから採取されたNK細胞)は見逃しません。そこが生きている細胞と人間が後から考えついた技術の差でしょう。
ともあれ、話題先行な部分のあるがんゲノム医療ですが、現状を変えていくきっかけには出来るのではないでしょうか。がんの性質から考えれば、明らかに使えるはずなのに、まだ保険適応になっていない分子標的薬は適応拡大するべきです。患者さんにとって目の前の選択肢が広がることになるなら、そこをもっと議論すべきです。
リンパ球バンク株式会社
代表取締役 藤井真則
三菱商事バイオ医薬品部門にて2000社以上の欧米バイオベンチャーと接触。医薬品・診断薬・ワクチンなどの開発、エビデンスを構築して医薬品メーカーへライセンス販売する業務などに従事。既存の治療の限界を痛感し、「生還を目指す」細胞医療を推進する現職に就任。