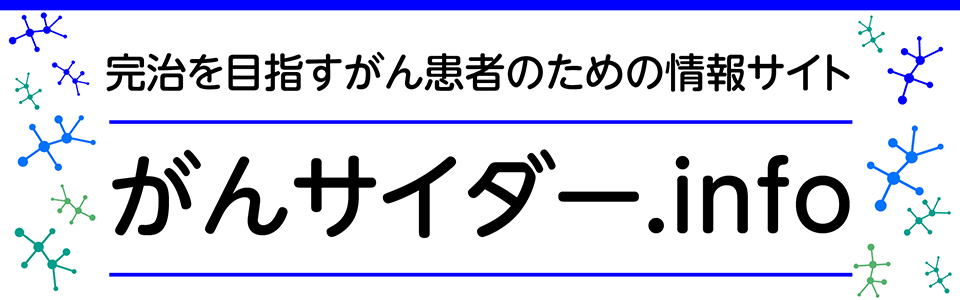3.抗がん剤の正体は殺細胞剤
 抗がん剤の大半は殺細胞剤で、分裂中の細胞のDNAを破壊する作用があります。副作用、薬剤耐性、発がん性などの問題はありますが、標準治療においては進行がんの治療には不可欠とされています。
抗がん剤の大半は殺細胞剤で、分裂中の細胞のDNAを破壊する作用があります。副作用、薬剤耐性、発がん性などの問題はありますが、標準治療においては進行がんの治療には不可欠とされています。
通常、抗がん剤といえば殺細胞剤
標準治療の柱となっている三大療法のうち、主要な全身療法といえば、抗がん剤による化学療法です。抗がん剤は、がん細胞が散らばっている場合に有効な治療法とされています。転移がん、または転移が疑われるがんには、通常、抗がん剤が使われることになります。一般に「抗がん剤」と呼ばれている薬の大半は殺細胞剤(殺細胞性化学療法剤)です。
分裂中の細胞のDNAをばらばらに
この殺細胞剤の作用について解説しましょう。全身に浸透して、攻撃の網を張った殺細胞剤は、分裂中の細胞があると、DNA(遺伝子の鎖)を狙い撃ちにします。細胞は増殖するために分裂する時だけ、DNAが無防備な状態になります。そのDNAに殺細胞剤がくっつくと、分裂・増殖の過程で鎖がばらばらになってしまうのです。
正常な細胞も必ず巻き添えに
1個の細胞が2つに分裂して増えるのは、正常な細胞でもがん細胞でも同じです。殺細胞剤が攻撃する際には、がん細胞だけを選んでいるわけではなく、あくまでも分裂中の細胞を標的にしているので、正常な細胞であっても、分裂中なら巻き添えになってしまいます。それが抗がん剤の副作用の正体です。腸の粘膜や骨髄、毛根など、新陳代謝が早い組織の細胞は、頻繁に分裂しているので、ダメージを受けやすくなります。殺細胞剤による治療中やその後に下痢などの消化器症状、免疫力の低下、脱毛といった副作用が出やすいのはそのためです。
 分裂中でないがん細胞は生存
分裂中でないがん細胞は生存
一方、治療中に分裂していなかったがん細胞は、殺細胞剤の網の目をかいくぐって生き延びます。1回投与しただけでは、がん細胞の全てを殺せないため、休薬期間を置いて、何回も投与されます。休薬期間を設けるのは、正常な細胞を殺し過ぎることによる副作用を軽減するためです。しかし、この性質上、全てのがん細胞を殺し尽くすのは困難だということになります。
薬剤耐性、発がん性という問題
また、どんな殺細胞剤にも使い続けるうちに効かなくなってしまうという限界があります。それが「薬剤耐性」です。さらに、休薬期間を設けたとしても、2年以上使い続けることは危険だとされています。あらゆる細胞のDNAを傷つけるので、それ自体に発がん性があるからです。
抗がん剤のデメリットを踏まえた上で
標準治療に欠かせない抗がん剤には、副作用など矛盾した面があります。しかし、がんという難敵を克服する上では、有効な武器には違いありません。昨今、その副作用の深刻さから完全に否定する意見がありますが、短所や限界を理解した上で、いかに効率よく使うかが、進行がん治療の鍵となります。また、進行がんを克服するためのもうひとつの課題として、全身療法といえば抗がん剤頼みになる標準治療の限界を、免疫系の全身療法によって補うことも大事だと指摘されています。