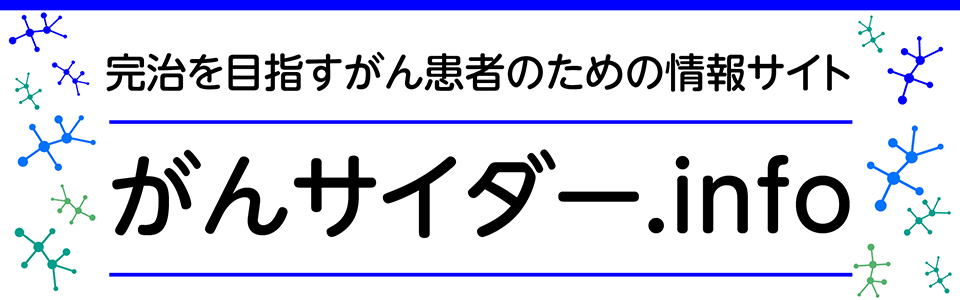2.免疫療法の原点「コーリーの毒」
 19世紀末、米国ではがん患者を人為的に伝染病に感染させ、がんの自然退縮を狙う治療法が試みられました。「コーリーの毒」と呼ばれ、今日の免疫治療にもその教訓が活かされています。
19世紀末、米国ではがん患者を人為的に伝染病に感染させ、がんの自然退縮を狙う治療法が試みられました。「コーリーの毒」と呼ばれ、今日の免疫治療にもその教訓が活かされています。
がんの自然退縮の再現は荒療治
がんの発症には必ず免疫力の低下が関わっています。逆に免疫が強く刺激されると、がんが自然に消えるようなことがあります。がんの自然退縮という現象があることは、昔から知られていました。しかし、それを再現しようとすると、とんでもない荒療治になります。がんが自然に消えるほどの免疫刺激は、がんより危険な病気(重い伝染病)にかからなければ起こらないからです。
人為的に丹毒に感染させる
19世紀末の米国で実際にその荒療治を試みたのがウィリアム・コーリー外科医でした。この治療は今日でも「コーリーの毒」として知られています。彼は丹毒(溶血性連鎖球菌による感染症)にかかった患者のがんが消えるのを目の当たりにして、過去のがん自然退縮例を徹底的に調べました。そして、がん患者に人為的に溶血性連鎖球菌を感染させるという思い切った治療を行ったのです。すると、丹毒にかかった後に回復し、がんも消滅して助かる患者が、何人も出ました。しかし、丹毒自体で命を落とす患者も少なくなかったのです。
穏やかな免疫刺激では効果がない
大きな危険を伴うコーリーの毒は、直後にX線が発見されて、放射線療法が始まった影響で、表舞台から消えていきました。その後、より穏やかに免疫を刺激する方法が試みられましたが、何の効果もありませんでした。例えば、現在も使われているがん治療薬のピシバニールは、乾燥した溶連菌を主成分としていますが、安全なので単独でがんを治すまでの刺激にはなりません。
「コーリーの毒のジレンマ」という大原則
コーリーの毒はがん治療法として定着はしませんでしたが、免疫治療に重要な教訓を残しました。激甚な急性症状を伴う危険な免疫刺激を加えないと、十分ながん治療効果は期待出来ないという大原則です。効果がある免疫刺激は危険、安全な刺激には効果がない。この矛盾を「コーリーの毒のジレンマ」といいます。
効果と安全性を両立する免疫細胞療法
闘病には体力が必要ですが、体によい栄養を摂取する程度では、残念ながらがんが消えるほどの免疫刺激は期待出来ません。コーリーの毒のジレンマを何とかクリアする方法として考案されたのが、体の外にNK細胞を取り出して活性化する免疫細胞療法です。1980年代に米国で大規模臨床試験が行なわれたLAK療法では、その有効性を証明してみせました。21世紀の日本ではその改良型がANK療法として実施されています。