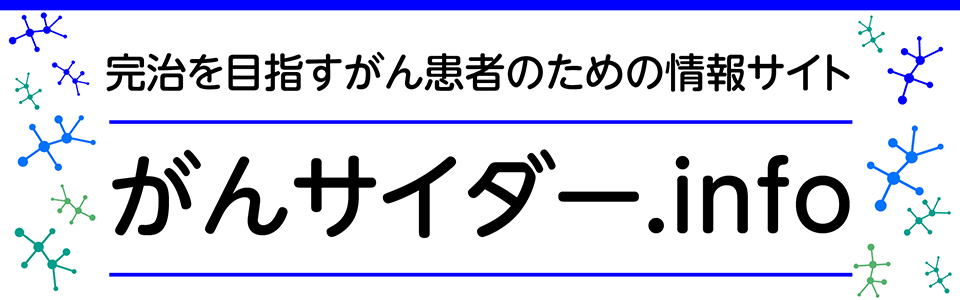5.免疫治療の様々なアプローチ
 がん免疫治療には歴史上、様々なアプローチがあり、安全な免疫刺激ではがんを治せないことがわかっています。そのジレンマを克服したのが免疫細胞療法です。
がん免疫治療には歴史上、様々なアプローチがあり、安全な免疫刺激ではがんを治せないことがわかっています。そのジレンマを克服したのが免疫細胞療法です。
丹毒の治癒とともにがんが消失
19世紀末の米国で試みられたがん免疫治療が、「コーリーの毒」という方法です。重い感染症が治った時に、腫瘍も消えているというがんの自然退縮は、昔からまれに観察されてきた現象です。そこで、コーリー医師は丹毒の病原菌(溶血性連鎖球菌)を患者に感染させて、がんの自然退縮を再現しようとしたのです。
コーリーの毒のジレンマ
しかし、丹毒が治って、がんも消えた患者がいた一方で、丹毒自体で亡くなる患者も続出しました。コーリーの毒は危険過ぎたため、やがて廃れてしまいます。ただ、コーリーの毒は免疫治療に大きな教訓を引き継ぎました。それは命を脅かすほどの刺激でなければ効かない、安全な刺激ではがんは治らないということです。これは、「コーリーの毒のジレンマ」として知られています。
安全な刺激では意味がない
1970年代、現代的ながん免疫療法の研究に最初の波が生まれました。体内に何かを投与して免疫反応を引き起こそうとするBRM療法です。発想としては機能性成分で免疫力を高めるサプリメントに似ています。BRMの代表は現在でも使われている免疫賦活剤です。例えば、キノコ製剤のクレスチンやレンチナン。また、微生物製剤としてコーリーの毒にも使われた溶血性連鎖球菌を無毒化、乾燥したOK-432(ピシバニール)や、結核菌を使った丸山ワクチンなどがあります。コーリーの毒のジレンマからわかるように、これらは刺激が弱く安全なので、決定的ながん治療法にはなりえませんでした。
サイトカインの大量投与は危険
1980年代には免疫細胞を活性化するサイトカイン(細胞が分泌する物質)が量産されるようになりました。そして、それを体内に投与して免疫を刺激するサイトカイン療法が模索されます。C型肝炎治療薬として知られるインターフェロンも、サイトカインの一種です。現在も抗がん剤として一部の白血病、脳腫瘍などの治療に使われています。インターロイキンと呼ばれるサイトカインのうち、IL-2(インターロイキン2)はNK細胞を増殖、活性化させる因子です。但し、これを体内に大量投与すると、強い副作用が出て、やはり危険でした。
安全性と効果を両立したLAK療法
体内に何かを投与しても、安全では効き目がなく、効果を上げようとすれば危険。このジレンマを解決方法として考えられたのが、NK細胞を体外に取り出し、IL-2で活性化させてから、体内に戻す免疫細胞療法でした(養子免疫療法とも呼ばれます)。特に1984年、米国のNIHで行われたLAK療法が有名です。体外循環させた大量の血液から、NK細胞を含むリンパ球を採取し、IL-2とともに3日以内の培養をしてから、一気に体内に投与するという強力な免疫細胞療法でした。同時投与したサイトカインの副作用で命を落とす患者もいましたが、標準治療が効かない数百人の患者全員に、何らかの効果を発揮し、15~25%に腫瘍半減以上の効果、一部では完全にがんが消えて再発しないという効果を上げました。これが今日の免疫細胞療法の原点です。
NK細胞の培養が難題だった
NK細胞の培養が非常に難しいため、米国ではLAKの実用化は断念されましたが、我が国では10年以上かけてNK細胞の培養技術を確立し、安全性と効果を両立。ANK療法として一般診療が始まっています。